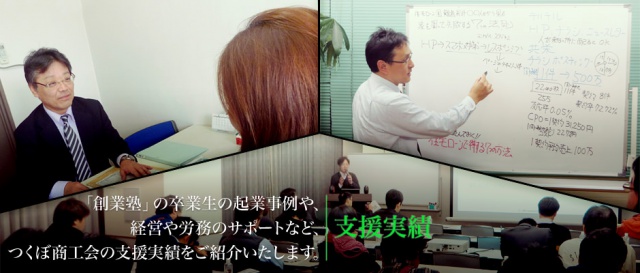倉敷刀剣美術館
| 企業名 |
倉敷刀剣美術館 |
役職 | 代表 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表者氏名 | 佐藤 均(さとう ひとし) | ||||
| 所在地 | 〒710-1101 岡山県倉敷市茶屋町173 | ||||
| TEL | 086-420-0066 | 業 種 | 美術刀剣販売 | ||
| URL | http://www.touken-sato.com/ | 定休日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) | ||
1 事業の概要
平成8年12月、現在、倉敷刀剣美術館館長である佐藤均さんは16年の刀剣専門店勤務の後、個人事業で美術刀剣・日本刀販売業を開業した。刀剣・日本刀販売業と言うとなかなかイメージが沸かないが、骨董、アンティーク分野に属する商品である。
平成14年、元銀行の跡地を購入しリノベーションを行い、倉敷刀剣美術館をオープンさせたのである。そして、平成15年には、「受注支援サイト吉備きびスクエア」に参加し、SEO対策によって中小企業にもビジネスチャンスがあることを知り、本格的にインターネットの活用に取り組むようになっていったのである。
2 ネットが無かったら潰れていた!
平成14年に経営指導員から「受注支援サイトに参加しませんか?」と声をかけられたことが「受注支援サイト吉備きびスクエア」に参加するきっかけとなった。その頃の佐藤氏はあまり、ホームページというモノを重視しておらず、「これからの時代、ホームページくらい無いとだめだろう」という程度の認識であった。また、それまでの商工会の支援についても「決算申告、会計ソフト導入、金融の支援等、どれも個人事業主である私にとってとても重要な支援であった。しかし、あの当時を振り返ると商工会から『ホームページの活用に参加しませんか?』と誘われなかったら美術館設立に伴う先行投資額が巨額だった為、倒産していたかもしれない。」と佐藤氏は言う。
実際、新店舗をオープン後の売上はアップした。しかし、その後、厳しい状況に陥ったそうであるが、それを打破したきっかけは「ホームページ」だった。特に、佐藤氏は「対面販売」に強いこだわりをもっており、ホームページで完結させる商売をあえて行わず、あくまで「来店促進」に特化し活用したことが成功のポイントであった。
その後、経営革新計画の承認を経営指導員からすすめられ、自社のビジネスを分析してみると自社の優良顧客は「関東中心の富裕層」のボリュームが多いことが明確になった。そこで、遠隔地に対して効果的な「ネットショップ」や「下取り・買取をネット上で展開してはどうか?」と経営指導員から提案を受け、平成18年に買取サイト「刀剣佐藤」を構築し運営を開始することでビジネスモデルの転換を図っていったのである。
3 経営革新計画にチャレンジ!そして、ネットショップが大ブレイク
そして、平成24年度には、過去に1度承認を得ていた「経営革新計画」に再度チャレンジを行った。その内容は、「ネットショップとオリジナル刀剣鑑定書発行事業による収益向上」であり、このテーマで2度目の「経営革新計画」の承認を岡山県知事から得ることができたのである。
それによって、ネットショップ「刀の蔵」を開店させると爆発的に売上がアップした。今までの対面にこだわって商売して来ていたお客さまから注文だけで無く、従来無かったお客様からの受注がドンドン増えていったのである。その実績としては、年商が4億円を突破という実績をあげ、一気に業界地図を塗り替える事に繋がっていった。
4 商工会の行った支援内容
(1)ネットショップの改善のために専門家派遣
公的な専門家派遣制度を活用し、ネット通販の専門家を複数派遣し、個別コンサルティングを実施した。特にお客様の動きを分析し、ユーザビリティの向上を目的に実施した。
また、商工会が専門家と連携し継続的な指導を行い、その結果、大幅な売上アップに繋がった。
(2)買取サイトの提案と構築支援
これによって新たなビジネスの展開が可能になった。
また、従業員の目利き力アップに繋がるなどこのサイトの出現が新たなビジネスモデルを生み出す
ことになった。
(3)おかやまIT経営力大賞の優秀賞を受賞
中小企業のIT活用を表彰するこの制度の応募した結果、取り組みを評価され優秀賞を受賞。
また、つくぼ商工会も支援者として特別賞を受賞した。
5 小規模事業者でもやればできる!
倉敷刀剣美術館は従業員が3名の小規模事業者であるが、IT活用によって業界地図を塗り替えるような事をやってのけた意義は大きい。
代表の佐藤氏は常々このように言っている。「小規模零細企業もやればできることを証明したい。また、地域の小規模事業者が成功事例になっていかなければならない。そうすることが商工会から受けた支援に対する恩返しだ」
そんな佐藤氏の情熱が、次々と新たなビジネス展開を行う原動力になっていると感じた。